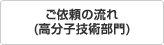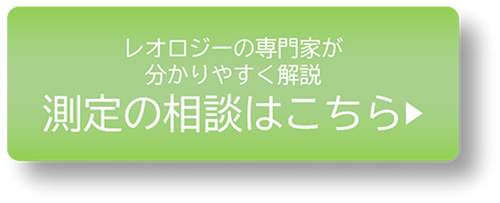業務案内
- Home
- 業務案内
- 材料・成分の総合評価(ゴム・プラスチック等)
- レオロジー・粘弾性
粘弾性
レオロジー
レオロジーは、対象に外力を加え応答を議論する学問です。外力に対する応答の関係から対象の応答性の違いを比較評価します。対象は、物質に限らずいかなるものにも適用でき、測定対象によって高分子レオロジー、ケモレオロジー、バイオレオロジー、サイコレオロジー、ヘモレオロジーのように呼ばれます。
本機構では、高分子材料(ゴム、プラスチック)に加えて、液体、金属、セラミックス等の評価についても受託試験、技術相談に対応しています。
レオロジー測定の目的
レオロジー評価は、
- 材料選定比較用の粘弾性データの取得
- 実際の成形や使用環境に合わせた測定
- CAE成形加工業界で広く使用されているComputer Aided Engineeringの略、実試験・実成形をせずにPCで変形・成形シミュレーションし、製品の物性・成形の良し悪し等を予測する技術(Computer Aided Engineering)用のデータ取得
の目的でよく使用されます。
レオロジー測定から分かること(弾む/弾まない)
例えば、おもちゃのゴムボールやスライムを床に落とすと弾む場合と弾まない場合があります。レオロジーの動的粘弾性測定で材料の持つ弾性(弾む)と粘性(弾まない)の度合いである損失正接を評価できます。
-
- 弾むスライムと弾まないスライム
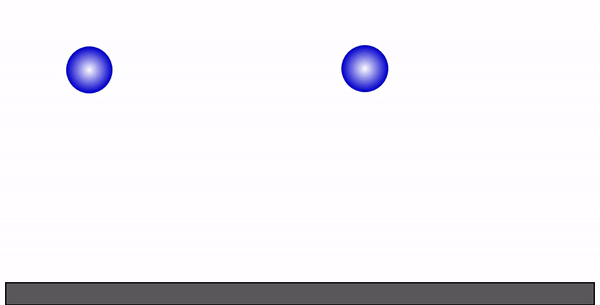
-
- 2種類のスライムの実際の落下実験
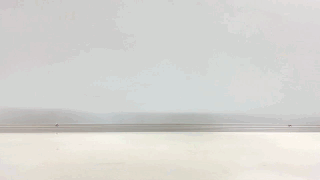
弾性(弾む):与えたエネルギーは貯蔵され反発力になる。
粘性(弾まない):与えたエネルギーは熱エネルギーに変換される。
材料の弾性及び粘性は、材料種(分子構造、分子量、分子量分布、架橋密度、固体充填量等)及び床に衝突した際の変形速度に依存します。詳細は、周波数依存性測定及び動的粘弾性試験と振り子を参照。
動的貯蔵弾性率が大きい程(損失正接が1より小さくなる程)材料は弾み
動的損失弾性率が大きい程(損失正接が1より大きくなる程)材料は弾まなくなる。
測定項目
・動的貯蔵弾性率:変形の際に試料に貯えられたエネルギーの尺度
・動的損失弾性率:変形の際に、発熱等により試料から損失したエネルギーの尺度
・損失正接:動的損失弾性率を動的貯蔵弾性率により除した値、値が大きいほど粘性が大きい
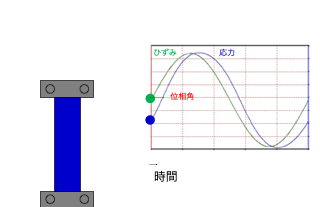
レオメータ(動的粘弾性装置、粘度測定装置)と装置選択
レオロジー測定では、得意なひずみ領域、試料の状態、試料の性質、変形モードによって使用する装置を選択します。それぞれの分類を表に示します。
| ひずみ領域 | 試料の状態 | 試料の性質 | 変形モード | 主な対応装置 |
|---|---|---|---|---|
| 線形粘弾性 (非破壊) |
固体 | 柔らかい | 引張、圧縮、曲げ | RSA-G2 |
| ねじり | ARES-G2 | |||
| 硬い、厚い | 引張、圧縮、せん断、曲げ | DMA+1000 | ||
| 未反応ゴム | せん断 | RPA2000 | ||
| 液体・溶融体 | せん断 | ARES-G2 | ||
| 非線形粘弾性 (大変形) |
固体 | 柔らかい、薄い | ねじり | ARES-G2 |
| 硬い、厚い | 引張、圧縮、せん断、曲げ | DMA+1000 | ||
| 未反応ゴム | せん断 | RPA2000 | ||
| 液体・溶融体 | せん断 | ARES-G2 |
| せん断速度領域 | 試料の状態 | 試料の粘度 | 変形モード | 主な対応装置 |
|---|---|---|---|---|
| 低速せん断(100/s以下) | 液体・溶融体 | 低粘度〜中粘度 | せん断 | ARES-G2 |
| 高速せん断(10/s以上) | 液体・溶融体 | 中粘度〜高粘度 | せん断・(伸長:cogswellによる) | RH2200 |
実際の成形や使用環境に合わせた測定を行うために
実際の成形や使用環境に合わせたレオロジー評価をする上で、材料がどのような変形をどのくらい受けるかを知ることが重要です。変形速度によって材料の粘弾性挙動が変わるため、変形速度を知ることは不具合改善のために有効です。
レオロジーで扱う変形は、大きく2つに分けることができます。
- せん断変形(せん断流動)
液体の輸送時の管内の流れ
材料混練時のスクリューと壁面での流れ
トランプの束の上面をスライドさせるような変形 - 伸長変形(伸長流動)
液体の輸送時の流動先端の流れ(ファウンテンフロー)
急縮小拡大流れ
材料が引張られたときの変形
風船を膨らませたときの変形
本機構のレオメータ
動的粘弾性装置
粘度測定装置
動的粘弾性試験の原理
レオロジー測定の種類
測定事例
- 温度依存性測定 〜タイヤの転がり抵抗・ウエットスキッド性評価〜
- ひずみ依存性測定 〜フィラーの分散性評価・Payne効果〜
- 周波数依存性測定 〜樹脂フィルムの周波数依存性評価〜
- 時間依存性測定 〜熱硬化性樹脂の硬化挙動〜 〜圧縮疲労試験によるへたり性の評価〜
- マスターカーブ(合成曲線)の作成 〜加硫ゴムの音響特性の評価〜
- せん断速度依存性測定 〜食品(はちみつとシロップ)の粘度評価〜
- 温度依存性測定 〜化粧品(ハンドクリーム)の複素粘度評価〜
- 温度時間換算則及びCox-merz則の適用 〜樹脂(高密度ポリエチレンHDPE)の粘弾性測定〜
- 一般化マクスウェルモデル近似及び離散型緩和スペクトル算出 〜樹脂(高密度ポリエチレンHDPE)の緩和成分分離〜
- 一般化フォークトモデル近似及び離散型遅延スペクトル算出 〜樹脂(高密度ポリエチレンHDPE)の遅延成分分離〜
- スペクトルを用いた粘弾性予測 〜樹脂(高密度ポリエチレンHDPE)の過渡応答予測〜